こんにちは、へぃへぃ。です!
毎月の給料から天引きされている「所得税」や「住民税」。
「なんでこんなに引かれるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
特に、子育て世代のサラリーマンにとっては、手取りが減るのは本当に痛い…。
「子どもの習い事代にまわしたい」「教育費をもっと貯めたい」と思っても、税金の壁が立ちはだかります。
実は、税金の仕組みを知らないと損することも多いんです!
以前に「所得税」には触れていますが、今回は、子育て世代のサラリーマンが特に気をつけるべき「所得税・住民税」の落とし穴について、考察していきます!
れっつごー!
① 住民税は「去年の収入」に対して課税される!
サラリーマンの住民税は、前年の所得に応じて決まります。
つまり、今年の給料が減ったとしても、昨年の収入が高ければ住民税はそのまま高いまま!
💡 例えばこんなケース…
✅ 育休復帰後、時短勤務にしたのに住民税が高い!
✅ 転職して年収が下がったのに、住民税が減らない!
✅ 会社を辞めたのに、住民税の支払いがドーンと来た!
特に注意が必要なのが、退職後の住民税。
住民税は6月から翌年5月までの1年分を払うため、退職後も前年の住民税を支払う必要があるんです。
📝 対策
🔹 転職や退職を考えているなら、住民税の支払いがどうなるか確認しておく!
🔹 退職後は一括払いを求められることがあるので、手元資金を確保しておく!
② 副業をしている人は住民税でバレる!?
最近は、副業をしているサラリーマンも増えていますよね。
ブログ、せどり、投資、YouTubeなど、少しでも家計の足しに…と頑張る人も多いはず。
でも、会社に内緒で副業をしている場合、住民税の金額が不自然に増えると会社にバレることがあります。
💡 なぜバレるの?
副業の収入が増えると、住民税も増加。
サラリーマンの住民税は会社が天引きして納付する仕組みなので、会社が「この人の給料に対して住民税が高すぎる…?」と気づくことがあるんです。
📝 対策
🔹 住民税の「普通徴収」を選択する(確定申告時に申請可能)
🔹 副業収入が増えてきたら、事業登録や法人化を検討する
③ ふるさと納税で節税できるのに、損していない?
ふるさと納税は、実質2,000円の負担で豪華な返礼品がもらえ、住民税や所得税が控除される制度。
でも、控除の上限額を知らずに**「思ったより節税されなかった!」**という人も…。
💡 上限額の目安(年収ベース)
| 年収(夫:会社員 / 妻:専業主婦) | ふるさと納税の上限額(目安) |
|---|---|
| 400万円 | 約43,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 |
| 700万円 | 約109,000円 |
控除の上限を超えて寄付してしまうと、単なる「寄付」になってしまうので要注意!
📝 対策
🔹 「ふるさと納税限度額シミュレーター」で計算してから寄付!
🔹 ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告不要!
④ 配偶者控除・扶養控除をしっかり活用する!
子育て世代の家庭にとって大事なのが、配偶者控除や扶養控除。
でも、年収の壁を意識しないと、せっかくの控除が受けられなくなることも…。
💡 ポイント
✅ 配偶者の年収が103万円以下なら「配偶者控除」適用
✅ 年収が103万円を超えても、150万円までなら「配偶者特別控除」適用
✅ 子ども(16歳以上)がいるなら「扶養控除」が使える
例えば、妻がパートをしている場合、年収130万円を超えると社会保険料の負担も発生し、手取りが減ってしまうことも…。
📝 対策
🔹 パートや副業の収入を調整しながら、控除をうまく活用!
🔹 子どもが16歳になったら「扶養控除」で節税できることを忘れない!
まとめ:賢く税金をコントロールしよう!
サラリーマンは「源泉徴収」で自動的に税金が引かれるので、あまり意識しないことが多いですが、仕組みを知るだけで節税できるポイントはたくさんあります!
✔ 住民税は前年の収入に対してかかるので、転職・退職時は注意!
✔ 副業の住民税で会社にバレるリスクあり!普通徴収を検討しよう!
✔ ふるさと納税の上限額を知って、しっかり節税!
✔ 配偶者控除や扶養控除を最大限活用しよう!
毎月の手取りを増やすためにも、税金の知識をしっかり身につけて、賢くコントロールしていきましょう!
へぃへぃ。でした。
「こんなことが知りたい!」というリクエストがあれば、ぜひコメントしてくださいね!
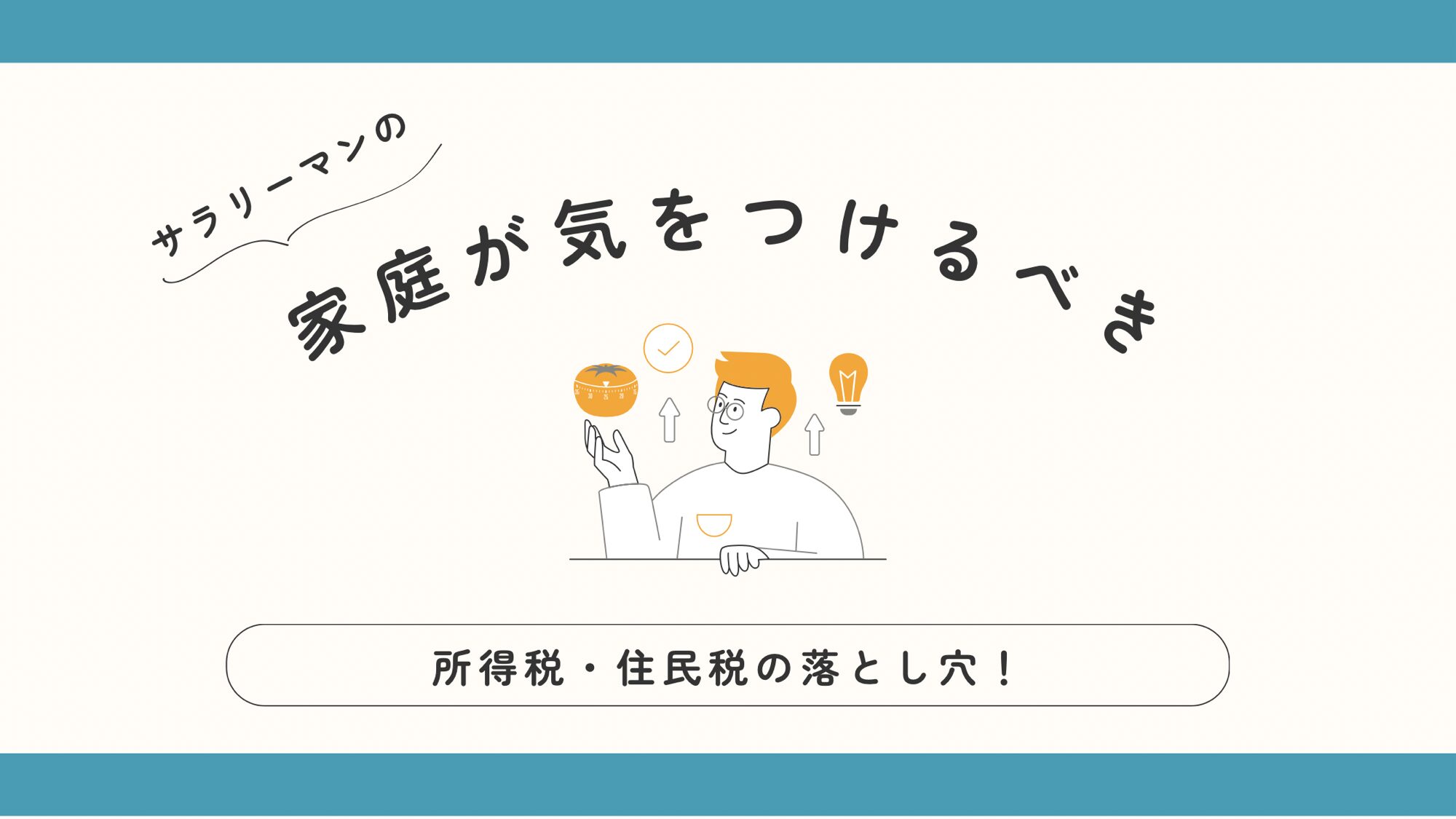
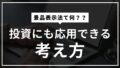

コメント